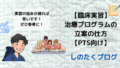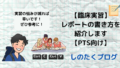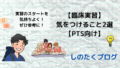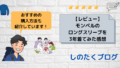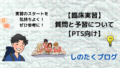臨床実習はただでさえ考えることが多く頭を悩ませますが、
ことが最難関と言っても過言じゃありません。
自分自身も学生時代に大変な思いをした一人です。
現在の実習環境は改善されたように思いますが、それでも
のは見受けられます。
知識や推論能力を測るためには仕方ないことだと思います。
それらの解決の助けになるように記事を書いてみます。
この記事を読むことで、日々提出する書類で好印象を与えることができ、実習が無難に乗り切ることができます!(保証はしませんが笑)
私自身は、
臨床実習指導者講習会修了
臨床実習指導12人経験
新人職員指導8人
脳卒中認定理学療法士
といった経歴を持っています。
その経歴から考えられる、

臨床実習の治療プログラムの立案の仕方を考えてみました!
最後までご覧ください!
正解はない

最初に言っておきたいのが、
正解は存在しない
ということです。
臨床実習における治療プログラムは、
考えている症例に即したベストな治療プログラムを考える過程を練習
しているので、
になります。
また、

参考文献は?何かあれば添付して。
と聞かれると思いますが、症例と全く同じケースを研究した文献は存在しません。
同じ診断名や経過を辿る人はいるかもしれませんが、全く同じ人生を辿る人はいないと思います。
ただ、
では妥当性に欠けます。
これは臨床に出てからもある程度同じことが言えますので覚えておいてください。
それを考える上でいくつかポイントがありますので順番に解説していきます。
一番の問題点を探す

治療プログラムを考える上で最初に行うことは、
です。
統合と解釈の後に治療プログラムが来るのにはきちんと理由があります。
ことが理学療法の目的です。
学校で学ぶICFの考え方は臨床でも用いられます。
まず問題点を考える上で、
それを達成する上で、問題となる動作を活動レベルで特定する
その活動に関する問題を、心身機能・身体構造のレベルまで落とし込んだもの
を用意すれば半分は済んだと思います!
プログラムの流れは先ほどの逆で、
活動
参加
のそれぞれに対応するように設定できると流れを順序よく考えられます。
例でいいますと、
トイレまで歩けるようにする、屋外歩行が可能になる(活動)
近所のスーパーまで買い物に行ける、友人宅を訪ねることができる(参加)
と言った形でミクロの視点とマクロの視点を使い分けて評価・介入していきます。
活動レベルで息詰まる場合には心身機能・身体構造のレベルに戻って考え直します。
問題点を探し出して本人HOPEとすり合わせを行うことで介入の道筋が見えてきます!
介入期間を考えるのは難しいけど逆算を利用する

問題点が見つかったらそこに対し介入を行いますが、
というのは新人職員だけでなく、既卒のスタッフでも予測が難しいものです。
まして経験がほとんどない状態でそれを考えるのは至難の技だと思います。
それでも、
ここまできたら次の介入を取り入れる
短期目標は◯◯週間で
長期目標は〇〇週間で
と考え出す必要はあると思います。
実習先の病期(急性期、回復期、維持期)でも大きく異なります。
そこで大切になってくるのが、実習の原則である
の流れです。
いきなり考えてきなさい!というのは実習の流れに反していると思います。
その後に一緒に考える経験をして考え方を身につけてます。
最後にケースの症例の目標期間と対応した介入内容について考える。
という流れが実習の正規のルートです。
ただ、流れに沿って教えてください!とは言いにくいと思うので考え出す必要性もあるかと思います。
そこで自分からのアドバイスは、
急性期なら、1ヶ月までの期間で逆算する
回復期なら、運動器疾患なら2〜3ヶ月で考える、脳血管障害なら4ヶ月で考える
維持期なら、本人HOPEについてしっかりと聴取し妥当な期間を検討する(一番難しいです)
それぞれ簡単に解説します。
急性期なら、1ヶ月までの期間で逆算する
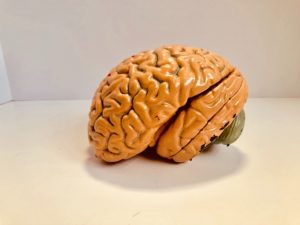
急性期とは受傷、発症してから過ごす場所です。
それに対し、長期目標は3ヶ月で〇〇と挙げても現実的ではないかと思います。
ケースの方の活動・参加レベルが向上することを考え、1ヶ月間は機能面への介入に特化することも選択肢だと思います。
その人が退院する方向性(自宅or回復期or施設)に応じた目標を最長1ヶ月の間で考えてみましょう!
回復期なら、運動器疾患なら2〜3ヶ月で考える、脳血管障害なら4ヶ月で考える

回復期でおさえたいのが、
ということです。
自宅へ退院することを目標に(本人もしくは家族が目標に据えて)入院する場所なので自宅に帰ることを念頭に置いて目標内容を期間を設定してください。
難渋するケースなどありますが、そう言った方をケースにすることは少ないと思います。
上記にある、運動器疾患なら2〜3ヶ月、脳血管障害なら4ヶ月で考えてみてください。
また、回復期病院を退院するとリハビリは週に数回、1回40分程度になります。
退院した後に目指せる目標というのは仕上げと言ったニュアンスが強いです。
入院期間が多少増えても退院後の目標を達成できる期間を立案してください!
維持期なら、本人HOPEについてしっかりと聴取し妥当な期間を検討する(一番難しいです)

維持期は急性期・回復期に比べ期間の設定が非常に難しいです。
期間が決まっていない場合は、ほとんどの場合が維持や介助量の軽減などざっくりしていることが多いですが、実習ではそれらは表記しない(できない)場合が多いです。
考えやすいケースを担当すると思いますが、それでも難しいと思います。なぜなら、
という状況が生まれるからです。
環境設定なども理学療法士だからこそできることがあると思うので最大限活用してみてください。
アドバイスを聞きながら考えていきましょう!
実習をうまく乗り切れると仕事が楽しくなる

実習での出来事や、感じた思いが今後の理学療法士としての仕事への取り組みに大きく反映されます。
この記事を読むことで、治療プログラムが立てやすくなり、臨床は楽しいんだと実習が終えられたら幸いです!!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事がいいなと思ったらシェアをお願いします!
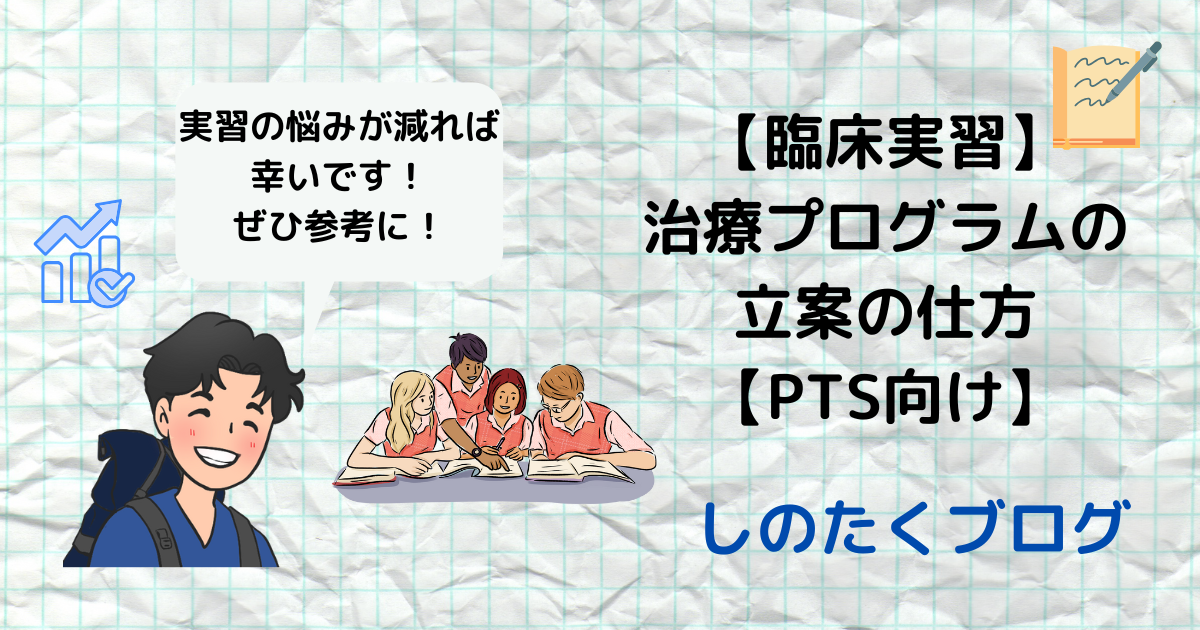
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a6d6e13.bfdc592e.2a6d6e14.36061ef2/?me_id=1259747&item_id=13271223&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2017%2F050%2F33681327.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c6db32d.4968f9b1.1c6db32e.a111d597/?me_id=1213310&item_id=11461654&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2602%2F26024442.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)